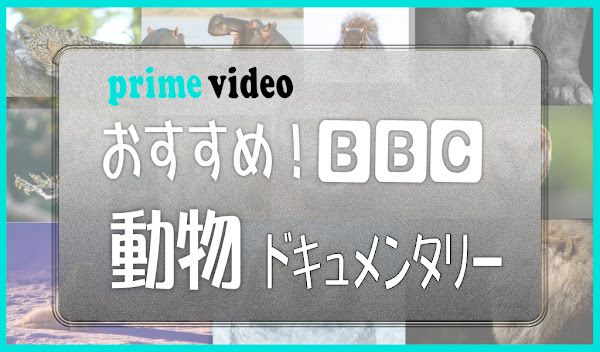世界を代表する山脈とは、どんな環境で、どんな野生動物が住んでいるのでしょうか?「ワイルド・マウンテン」は、ロッキー、ヒマラヤ、アンデスを舞台にしたBBC earth制作のおすすめドキュメンタリー作品。大自然の過酷な環境で動物や人間はどう適応しているのでしょうか?プライムビデオで見られます。
今回紹介する作品は、地球を代表する山脈をテーマにした「ワイルド・マウンテン」。「ロッキー山脈」「ヒマラヤ山脈」「アンデス山脈」を舞台に、それぞれの山脈の特徴を、その場所でしか見られない大自然の映像を見ながら、知ることが出来ます。
「BBC earth」作品なので、山脈に住む野生動物が続々と登場します。 人が住むには厳しいこの環境で、動物たちはどのように適応しているのでしょうか?
また、人間たちの生活や活動にも触れています。高地で住む人々はどんな生活をしているのでしょうか?危険な場所でアクティビティに挑戦する人も紹介されています。
ワイルド・マウンテン 荘厳なる峻嶺

今作は、「ロッキー山脈」「ヒマラヤ山脈」「アンデス山脈」の全3話。山脈ごとの自然環境、生息している動物、人間の関わりなど、特徴がよくわかる内容になっています。
第1話「ロッキー山脈」
24時間で気温が56度下がった記録があるほど、気候の変動が激しいロッキー山脈。カナダの北部からアメリカのニューメキシコ州まで、全長4800mを超える長さです。 場所によっては、山火事や雪崩がしょっちゅう起こる厳しい環境です。四季ごとに、山は大きく姿を変えるこの環境で、野生動物や人間たちはどのように対応しているのでしょうか?
野生動物たち
悪魔のモデルのような顔をしているビッグホーン。繁殖期は、その自慢の角で争います。雪に埋もれた死体を探すグズリ。せっかく見つけた獲物も生存競争が激しい自然界では、独り占め出来ません。
ホラー演出
今では廃墟となった炭鉱の跡地では、ミュールジカを狙う捕食者が、ホラー映画のような演出で登場します。 春に生まれたアメリカアカシカ。生後間もない子鹿の3分の1は、捕食者の餌食になってしまいます。一人で身を隠す子鹿は大丈夫なのでしょうか?
自然界のバトルロワイヤル
草原に出来た池は、夏の暑さで干上がっていきます。そこで生まれたサラマンダーは、水が干上がってくると、体が大きく変体します。ここから大自然のバトルロワイヤルが始まります。
ハチドリの旅
秋にはアカフトオハチドリが子育てをします。この小さなハチドリは、とんでもない距離を移動する渡り鳥でした。ロッキー山脈の南を目指して飛び立ちます。
人間
ヘリコプターでとんでもない場所に降ろされた女性。目的は常人には理解できない場所でのスキーでした。 今度は、常人ではびびってしまいそうな崖っぷちに座る男性が登場。ムササビスーツを着て、とんでもない場所から飛び降ります。
ロッキー山脈の大自然を馬で走る男性も登場します。 ネイティブアメリカンの伝統行事には、クラを使わず3頭の馬に乗り換えながら行うレースがあります。家族でレースに挑みます。
第2話「ヒマラヤ山脈」
ヒマラヤ山脈の標高は、ロッキー山脈の倍。標高7000mを超える山が100以上あり、その内14の山が8000mを超える地球で最も高い山脈です。パキスタンから中国に渡って、連なっています。 この作品では、標高に沿ってストーリーが進んでいきます。
標高2500m
中国の標高2500mの地域では、地球上でもっとも高い場所に住むサル・ウンナンシシバナザルが、-28度にもなる極寒の森で過ごしています。この森では、群れに入り、体を寄せ合って過ごさなければ、冬の寒さは乗り切れません。 ひとりぼっちの若いオスは、このままでは死んでしまいます。序列の厳しいオスのグループに仲間入り出来るのでしょうか?
キッバル村
ヒマラヤでは、冬には孤立してしまう厳しい環境で過ごす人々もいます。インドのキッバルもその一つ。生命線は家畜。 しかし、夜になると家畜が獣に襲われてしまう問題が発生します。夜間は家畜を家にいれて対応する人たち。獣の正体と、その対処方法にせまります。
キッバル周辺の山々は標高が6000mを超え、山頂は雲よりも高い位置にあります。モンスーンの時期には、4ヶ月で300億トンの大量の雨が降ります。その影響で、山から大量の水が流れ、様々な影響を及ぼします。スケールのでかい、大自然の仕組みがよくわかります。
鍾乳洞
水の勢いで作られた巨大な鍾乳洞は、厳しい気候の影響を受けず、冬から夏の間でも5度の温度に保たれています。この完璧な環境を利用しているのがキクガシラコウモリ。鍾乳洞に住むことで、厳しい自然環境の影響を受けずに生活しています。
標高3000m
標高3500mで修行するチベット僧。彼が向かうのは、山の斜面にある洞窟が修行場所。ここで8ヶ月間ひたすら瞑想をします。その間の熱源はロウソクのみ。常人にはできそうもありませんね。悟りは開けるのでしょうか?
北インドのピヤン僧院では、砂曼荼羅と言われる伝統ある芸術作品が作られます。
標高4000m
高地に住む動物たち
標高4000mに住むのはプレーリドッグのような、かわいいヒマラヤマーモット。8ヶ月の冬眠のために、12週間の間に体重を3倍に増やさなければなりません。そのため、マーモット同士での縄張り争いが繰り広げられます。
マーモットを捕食する動物も多く、ちらっと登場するのがヒマラヤヒグマ。きぐるみのようです。本当に一瞬ですが、クマ好きとしては、見逃さずぜひ見てほしい一コマです。ヤクの群れが生み出す、自然の循環も見られます。
標高4200mの乾燥したチベット高原でも、野生動物は生息しています。-40度の寒さに耐えられるチルー。水を何週間も飲まずに過ごせるチベットノロバ。世界で最も高地に住むチベットオンセンヘビ。名前のとおり温泉につかり、体を温めます。
標高5000m以上
無謀な挑戦?
標高5200mのエベレストのベースキャンプでは、なんとエベレストマラソンが行われます。 高地を走って下っていき、村がゴールです。酸素量が地上の半分しかなく、体への負担がやばいこのレースでわかるのが、環境に適応している地元の人々の能力。
欧米で鍛えた人でもすぐに歩いてしまうこの場所で、地元の人たちはゴールに向かって走り続けます。
最後の生き物
エベレストハエトリが住むのは、なんと標高6700m。生き物が生息できる限界の高さ。-20度にも耐えることが出来る小さいクモ。なぜこんな場所に生息しているのでしょうか?
世界の天井
標高8000mになると、生き物が存在しません。登山者がSゾーンと呼ぶ場所で、酸素濃度があまりに低いため、体の機能が停止し始める領域です。
登山者が標高8848mの頂上にいられるのは、わずか15分。頂上で得られる達成感とそこからしか見れない景色が、エベレストを登らせるのでしょうか?
第3話「アンデス山脈」
アンデス山脈はベネズエラからチリにまたがる、世界で最長の山脈です。 木の育たない風の強い場所や、カラカラの砂漠、大自然の作る絶景、生物の楽園など、地域よって様々な顔を見せてくれます。過酷な環境に適応する野生動物や、こと土地に住む人たちはどんな生活をしているのでしょうか?
アンデス南部
南端のホーン岬から始まるアンデスの南部は、秒速40mの風が吹き、天候も急激に変わる過酷な環境です。 そこに住むピューマの親子。生後4ヶ月の3匹の子供を育てるには、4日に一度は獲物を狩る必要があります。狙うのは素早くてでかいグアナコ。ピューマはころころ変わる天候でどのような狩りをするのでしょうか?
乾燥した砂漠
チリにあるアタカマ砂漠は世界で最も乾燥した場所です。湖の水は塩水。この過酷な環境に住んでいるのがヤマイグアナ。生物に水は必須です。飲み水のほとんどないこの場所で、どのように水を得るのでしょうか?
中央アンデス
アンデス山脈のには200をこす活火山があります。 マグマ溜まりでは、10年で2メートル盛り上がった例もあります。 もくもくと吹き上がる灰は、大自然の凄さを感じさせます。
最も美しい場所
ボリビアの標高3500mの場所には、絶景でも有名な、世界最大の塩の平原・ウユニ塩湖があります。普段は水がなく、あるのは塩だけです。 豪雨が降ったあとのこの場所は、見るものの心を奪う、唯一無二の絶景に変わります。
インカ帝国の技術
ウユニ塩湖を300キロほど北上すると、まっ平らな地形とは打って変わって、デコボコな険しい山岳地帯が姿を見せます。マチュピチュが有名な、インカ帝国が栄えた場所です。
この地域では、インカ帝国の高度な建築技術を受け継います。住民たちによる草を使った伝統的かつ、生活に必須の建築物が見ることができます。
メガネグマの記憶
雨がめったに振らず、気温は日陰でも40度に達する中央アンデスでは、動物も水分補給に苦労します。 この環境に適応しているのが、メガネグマ。垂直に近い斜面も器用に降りる、少し小型のクマです。
この地では水の湧く場所が限られていますが、記憶力の高いこのクマは、その場所を覚えており、ときには水浴びをして楽しみます。
おじさんの危険な日常
アンデスの山道をバスで運転するおじさんが登場。 すごいのはその道。当然のように舗装されておらず、ガードレルのない細い道を走る大型のバス。日本人ならぞっとする光景です。
ペルーの山脈
ロッククライミング
ペルーのパロン谷。ここはアンデスでは珍しい花崗岩の山。 ここの岸壁に挑むロッククライマーが登場。標高5000メートルのこの場所では、酸素の量も地上の半分。すごい斜面を登っていきます。
高山地帯
コルディエラ・ブランカと呼ばれるペルーの山脈では、ペニテンテスと呼ばれる 高さ6メートルの刃のような氷が連なる、アンデスでしか見られない不思議な自然現象が見られます。
この標高5500mの氷冠にはハジロジュウカチョウという鳥が住んでいます。 この鳥は氷河の中に巣を作ります。氷河が溶ける前に、ヒナはここから巣立たなければなりません。未来には不安が残ります。気温上昇で住処が消滅しつつあるからです。
生物の楽園
エクアドルの赤道付近には雲霧林が広がるジャングルがあります。 標高2000mでも気温は15度、雨もよく降るこの場所は何万種類の生き物がひしめきある動物たちの楽園です。このジャングルだけで特集してほしいほど、魅力が溢れています。
擬態能力
生存競争の激しいこの場所では、トゲトゲのナナフシや半透明のカエルなど、擬態にすぐれた生物たちを見ることができます。中でも2014年に発見されたプリスティマンティス・ミュータビリスという名のカエルは、体を変形させ驚くべき擬態能力を見せてくれます。これでは見つかりません。